前の10件 | -
壱岐旅行ちょっと福岡 [旅・出張]
壱岐に行ってきました。
以前対馬に行ったとき、あまりに山がちなのにびっくりしましたが、対して隣の壱岐は平坦で農業にも向いている、とのことで、いつか行ってみたいなと思っていました。
ところがこれがなかなかの苦難で、そもそも今年の年明け早々に行こうと思ったら、羽田のJALと海上保安庁の飛行機の衝突事故で、福岡までの便が欠航になってしまって延期。
ホテルもレンタカーもキャンセル。
そして今度は福岡までの便に乗って、(飛行機が燃えちゃったせいか)国際線仕様の飛行機で、広くていいなとか喜んでいたら、機中で博多から壱岐までの船が欠航となったことを知りました。
福岡空港に着いてからばたばたと調整し、午後の高速船は既に満席となっていたので翌朝に変更。
ホテルに2泊から1泊への変更の電話をし、レンタカーはいったんキャンセルし、博多での1泊のホテルを確保(高い・・・)。
ここまでやって、博多でどうしようか考え、太宰府の九州国立博物館で、先日大阪の中之島美術館でタッチの差で見られなかった長沢芦雪展を見て、太宰府でお参り。
何か工事中で妙な建物になっていました。

福岡アジア美術館を見て、夜は中州で食べて飲んで。
久し振りに食べたアワビの地獄焼き+日本酒も最高だったし、バーでなぜか隣の若者二人組が一杯ごちそうしてくれました。これからキルホーマンを飲むときはおごってくれた二人を思い出そうと思います。
博多良いところ。
そして翌朝、朝一番の高速船は無事出航、思ったより混んでいませんでした。
そしてついに、ついに壱岐に上陸。
郷ノ浦ターミナルから電話してあっさりとレンタカーも借りられて、日程圧縮なので集中して観光開始。
まずは一支国博物館(いきこくはくぶつかん)で予習。
魏志倭人伝での記述が紹介されているが、そもそも何か一支国の字とか人数とか間違いが多いらしい。
弥生時代の原の辻遺跡の映像を見て、映像が終わるとスクリーンが上がって実際の景色が窓から見えるという粋な演出。
元寇の前に刀伊の入寇、さらには南蛮人奄美)が攻めてきたとのこと、
また、弥生式土器が朝鮮半島に渡ったり、朝鮮半島のものが見つかったりしていたらしい
原の辻遺跡まで歩いたが、とても風が強く、寒かった。
原の辻遺跡(はるのつじいせき)は、静岡県登呂遺跡、佐賀県吉野ヶ里遺跡に並ぶ国の特別史跡。
そし遺跡がある深江田原平野(ふかえたばるへいや)は長崎県で諫早に次ぐ平野。

まあ、吉野ヶ里遺跡もそうだし、三内丸山のような縄文に関もそうですが、建物が残っているわけではなく、図面が残っているはずもなく、柱を立てた穴の跡などから復元したものなので、まあ、テーマパークみたいなものですよね。
島内を反時計回りにまわっていって、はらほげ地蔵。
海に向かって地蔵が並んでおり、なんで作ったかもよくわからないらしい(諸説あり)。

そして、とにかく東からの風が強くて、台風のよう。
無事に着いたけれど帰れるのかちょっと不安に。

少弐公園には少弐資時の墓があります。
元寇は鎌倉武士が「神風」にも助けられて元を追い返したことになっていますが、2回とも緒戦の対馬と壱岐はほぼ全滅しています。
まさに多勢に無勢の中、奮戦した人達には頭が下がります。

そして最北の勝本浦。
車で行ってもかなり急な坂を下りることになります。
ここは重伝建であったりはしませんが、古い漁師町が残っていていいですね。
鶴と松の意匠が玄関の上に掲げられていて、どういう意味か、玄関に「鬼」と書いてある家もありました。

そして島の中央部には、弥生よりも時代を下って、古墳群が集中しています。
なんか石室も開放されているのですよね。
離島なのにこれだけ古墳が多いというのは不思議です。
平野があることもあって、昔から人口が多かったようです。

神社も多く、月讀神社(つきよみじんじゃ)という古事記っぽい名前の神社も。
ただ、神社はとても多い一方で、お寺は少なく、廃仏毀釈との関係が気になるところです。

日も暮れてきて、名前そのままの猿岩を見て観光は終了。
さすがに1.5日の予定が1日に圧縮されたのでばたばたです。

最後の日の朝、高速船乗り場まで歩いて橋を渡っていると、空き地に菜の花が満開になっているのが見えました。

以前対馬に行ったとき、あまりに山がちなのにびっくりしましたが、対して隣の壱岐は平坦で農業にも向いている、とのことで、いつか行ってみたいなと思っていました。
ところがこれがなかなかの苦難で、そもそも今年の年明け早々に行こうと思ったら、羽田のJALと海上保安庁の飛行機の衝突事故で、福岡までの便が欠航になってしまって延期。
ホテルもレンタカーもキャンセル。
そして今度は福岡までの便に乗って、(飛行機が燃えちゃったせいか)国際線仕様の飛行機で、広くていいなとか喜んでいたら、機中で博多から壱岐までの船が欠航となったことを知りました。
福岡空港に着いてからばたばたと調整し、午後の高速船は既に満席となっていたので翌朝に変更。
ホテルに2泊から1泊への変更の電話をし、レンタカーはいったんキャンセルし、博多での1泊のホテルを確保(高い・・・)。
ここまでやって、博多でどうしようか考え、太宰府の九州国立博物館で、先日大阪の中之島美術館でタッチの差で見られなかった長沢芦雪展を見て、太宰府でお参り。
何か工事中で妙な建物になっていました。

福岡アジア美術館を見て、夜は中州で食べて飲んで。
久し振りに食べたアワビの地獄焼き+日本酒も最高だったし、バーでなぜか隣の若者二人組が一杯ごちそうしてくれました。これからキルホーマンを飲むときはおごってくれた二人を思い出そうと思います。
博多良いところ。
そして翌朝、朝一番の高速船は無事出航、思ったより混んでいませんでした。
そしてついに、ついに壱岐に上陸。
郷ノ浦ターミナルから電話してあっさりとレンタカーも借りられて、日程圧縮なので集中して観光開始。
まずは一支国博物館(いきこくはくぶつかん)で予習。
魏志倭人伝での記述が紹介されているが、そもそも何か一支国の字とか人数とか間違いが多いらしい。
弥生時代の原の辻遺跡の映像を見て、映像が終わるとスクリーンが上がって実際の景色が窓から見えるという粋な演出。
元寇の前に刀伊の入寇、さらには南蛮人奄美)が攻めてきたとのこと、
また、弥生式土器が朝鮮半島に渡ったり、朝鮮半島のものが見つかったりしていたらしい
原の辻遺跡まで歩いたが、とても風が強く、寒かった。
原の辻遺跡(はるのつじいせき)は、静岡県登呂遺跡、佐賀県吉野ヶ里遺跡に並ぶ国の特別史跡。
そし遺跡がある深江田原平野(ふかえたばるへいや)は長崎県で諫早に次ぐ平野。

まあ、吉野ヶ里遺跡もそうだし、三内丸山のような縄文に関もそうですが、建物が残っているわけではなく、図面が残っているはずもなく、柱を立てた穴の跡などから復元したものなので、まあ、テーマパークみたいなものですよね。
島内を反時計回りにまわっていって、はらほげ地蔵。
海に向かって地蔵が並んでおり、なんで作ったかもよくわからないらしい(諸説あり)。

そして、とにかく東からの風が強くて、台風のよう。
無事に着いたけれど帰れるのかちょっと不安に。

少弐公園には少弐資時の墓があります。
元寇は鎌倉武士が「神風」にも助けられて元を追い返したことになっていますが、2回とも緒戦の対馬と壱岐はほぼ全滅しています。
まさに多勢に無勢の中、奮戦した人達には頭が下がります。

そして最北の勝本浦。
車で行ってもかなり急な坂を下りることになります。
ここは重伝建であったりはしませんが、古い漁師町が残っていていいですね。
鶴と松の意匠が玄関の上に掲げられていて、どういう意味か、玄関に「鬼」と書いてある家もありました。

そして島の中央部には、弥生よりも時代を下って、古墳群が集中しています。
なんか石室も開放されているのですよね。
離島なのにこれだけ古墳が多いというのは不思議です。
平野があることもあって、昔から人口が多かったようです。

神社も多く、月讀神社(つきよみじんじゃ)という古事記っぽい名前の神社も。
ただ、神社はとても多い一方で、お寺は少なく、廃仏毀釈との関係が気になるところです。

日も暮れてきて、名前そのままの猿岩を見て観光は終了。
さすがに1.5日の予定が1日に圧縮されたのでばたばたです。

最後の日の朝、高速船乗り場まで歩いて橋を渡っていると、空き地に菜の花が満開になっているのが見えました。

新島旅行 [旅・出張]
東京の島シリーズ、伊豆大島、八丈島、三宅島に続いて新島に行ってきました。
かなりばたばたで出かけたところ、レンタカーを予約しているのに運転免許証を家に忘れてしまい、レンタサイクル(電動)で回りました。
電動自転車って初めてでしたが、これ、良いですね。
新島と言えば何と言っても砂浜、ビーチです。
海はきれいだし、砂浜もゴミが落ちていなくてとてもきれいです。
シーズンオフ、人がおらず、独り占めでした。


新島の中心部、本村(ほんそん)の外れに新島村博物館があります。
テントのような不思議な建物。
人口2000人程度の村にしては充実しており、新島の地質から歴史、文化などを紹介しています。
新島は茄子のような形をしています。
こうしたいびつな島の形は、単成火山が複数つながったことによってできています。
南部の向山は800年代の噴火でできたらしい。
ここで採れる坑火石(コーガ石、こーがせき)は明治以降に発掘が本格化し、軽くて加工がしやすく、火事にも強いということで、島では建築にも広く使われています。
石でできた建物が多く、他の島と違った雰囲気を醸し出しています。

断崖絶壁が多い伊豆諸島の中で、砂浜が発達しているのは、新島固有の地質によって砂浜のもととなる砂が供給されているからとのこと。
村にはいくつか神社と寺があります。
大きなものとして、十三社神社と長栄寺。
長栄寺は日蓮宗のお寺。
もともと新島は真言宗が多かったが、日英が布教して日蓮宗になったそうです。

右奥に行くと村の共同墓地があり、ここも強い印象を受けました。
墓地なのに一面に白砂が引いてあって、通路と墓地の区画の区別がよくわかりません。
前田、梅田、宮川、植松などの名字が多い。
お彼岸でもないのに人が多く、そして多くの墓に花が飾ってあります。
よく見ると、造花も混じっているよう。
村人は信仰心が篤いようです。
一段低まったところに流人墓地として小さな墓石が並んでいました。
ここにも花が飾られていました。

伊豆諸島、冬は強い西風が吹くのだそうです。
夜中も強い風の音がしていて、無事に帰れるのかちょっと心配になりましたが、船は無事出航。
帰りの船からは薄暮の富士山が見えました。

かなりばたばたで出かけたところ、レンタカーを予約しているのに運転免許証を家に忘れてしまい、レンタサイクル(電動)で回りました。
電動自転車って初めてでしたが、これ、良いですね。
新島と言えば何と言っても砂浜、ビーチです。
海はきれいだし、砂浜もゴミが落ちていなくてとてもきれいです。
シーズンオフ、人がおらず、独り占めでした。


新島の中心部、本村(ほんそん)の外れに新島村博物館があります。
テントのような不思議な建物。
人口2000人程度の村にしては充実しており、新島の地質から歴史、文化などを紹介しています。
新島は茄子のような形をしています。
こうしたいびつな島の形は、単成火山が複数つながったことによってできています。
南部の向山は800年代の噴火でできたらしい。
ここで採れる坑火石(コーガ石、こーがせき)は明治以降に発掘が本格化し、軽くて加工がしやすく、火事にも強いということで、島では建築にも広く使われています。
石でできた建物が多く、他の島と違った雰囲気を醸し出しています。

断崖絶壁が多い伊豆諸島の中で、砂浜が発達しているのは、新島固有の地質によって砂浜のもととなる砂が供給されているからとのこと。
村にはいくつか神社と寺があります。
大きなものとして、十三社神社と長栄寺。
長栄寺は日蓮宗のお寺。
もともと新島は真言宗が多かったが、日英が布教して日蓮宗になったそうです。

右奥に行くと村の共同墓地があり、ここも強い印象を受けました。
墓地なのに一面に白砂が引いてあって、通路と墓地の区画の区別がよくわかりません。
前田、梅田、宮川、植松などの名字が多い。
お彼岸でもないのに人が多く、そして多くの墓に花が飾ってあります。
よく見ると、造花も混じっているよう。
村人は信仰心が篤いようです。
一段低まったところに流人墓地として小さな墓石が並んでいました。
ここにも花が飾られていました。

伊豆諸島、冬は強い西風が吹くのだそうです。
夜中も強い風の音がしていて、無事に帰れるのかちょっと心配になりましたが、船は無事出航。
帰りの船からは薄暮の富士山が見えました。

銚子旅行 [旅・出張]
2023年最後の旅行は銚子旅行。
人口や都市規模の割に有名な地名というのがあって、先日に行った与那国島もそうでしょう。
そして今回行った銚子もその1つ。
水産業(2023年は釧路に水揚げ量を抜かされてしまった・・・)、日の出、醤油生産で有名です。
利根川の河口、南側に町が拡がっていて、銚子大橋が架かっています。
川幅は結構広くて、流れも結構あります。
河口が広いと言えば、ラプラタ川の河口を思い出しました。あちらは対岸がとても見えないほど広いのですけれども。

銚子駅から有名な銚子電気鉄道で犬吠まで。
銚子電気鉄道とjRの駅は一体化していて、銚子電気鉄道の切符は乗車してから車内で買うので、駅員さんに声をかけて、自動改札の横を手ぶらで入場してホームまで行きます。
なんとなく変な感じです。
犬吠埼は、犬吠駅で降りてちょっと歩きます。
灯台の上まで登ることができ、資料館も併設されています。
周囲には店も並びます。

犬吠埼は日本の東端ではないのだけれど、地球の自転の角度が傾いている関係で、冬は一番早く日が昇り、初日の出を一番早く見られるのだそうです。
ということで元旦に混むようですが、年末でも人が多く、広い駐車場がいっぱいでした。
また犬吠駅まで戻り、通り過ぎてキャベツ畑の中を歩いて地球の丸く見える丘展望館があります。
知らなかったことですが、銚子はキャベツの大産地で、至る所でキャベツを育っています。
他の畑が見当たらないくらいです。

さらに銚子電気鉄道の終点である外川(とかわ)まで歩きました。
銚子の中心部は空襲を受けたこともあるのか広い道で風情はありません。
しかし、この外川地区は斜面に短冊状御区画が拡がり、民家や商店街が並び、静かな街を歩くのが楽しいです。

どうやら紀州の人達が移住してこの碁盤の目の町を作り、ここで挙げられた水産物を運ぶために銚子電気鉄道が作られたようですね。
太平洋岸には屏風ヶ浦と呼ばれる断崖絶壁が拡がっています。
海食崖で、下の部分と上の部分で不連続に時代が違う境界があります。
銚子は隆起していて、とても古い地層が残っているのだそうです。
崖の下には遊歩道が途中まであり、歩くことができます。
銚子は突端にあるので、日の出だけではなく海に沈む夕陽も見ることができます。
太平洋側なのに。

銚子ポートタワーにのぼり、市街を見渡すと、利根川が銚子を避けるように大きく蛇行して太平洋に注いでいる様子、対岸の茨城県の海岸沿いに工業地帯が拡がっている様子がよく見えます。
外房はかつて航海の難所であったため、太平洋岸を北から来た船はここから利根川に入り、江戸に入っていました。
そこで栄えたのが銚子港ということです。
さらに、銚子沖で黒潮と親潮が出会っていることで好漁場でもあります。
ただし、街に港町らしい歴史が残っていないのはちょっと残念。
年末の旅行なので、市場も閉まっていて新鮮な魚介を、とは行きませんが、食べたものは皆美味しく、諺解まで飲食した感じです。
ただ、まあ半島のようなところなので交通はちょっと不便で、電車の本数もそれほど多くないし、車で行くにも高速道路を降りてから結構走る必要があります。
銚子連絡道路というのが建設中で、途中までできているので、それが完成すると良いですね。
人口や都市規模の割に有名な地名というのがあって、先日に行った与那国島もそうでしょう。
そして今回行った銚子もその1つ。
水産業(2023年は釧路に水揚げ量を抜かされてしまった・・・)、日の出、醤油生産で有名です。
利根川の河口、南側に町が拡がっていて、銚子大橋が架かっています。
川幅は結構広くて、流れも結構あります。
河口が広いと言えば、ラプラタ川の河口を思い出しました。あちらは対岸がとても見えないほど広いのですけれども。

銚子駅から有名な銚子電気鉄道で犬吠まで。
銚子電気鉄道とjRの駅は一体化していて、銚子電気鉄道の切符は乗車してから車内で買うので、駅員さんに声をかけて、自動改札の横を手ぶらで入場してホームまで行きます。
なんとなく変な感じです。
犬吠埼は、犬吠駅で降りてちょっと歩きます。
灯台の上まで登ることができ、資料館も併設されています。
周囲には店も並びます。

犬吠埼は日本の東端ではないのだけれど、地球の自転の角度が傾いている関係で、冬は一番早く日が昇り、初日の出を一番早く見られるのだそうです。
ということで元旦に混むようですが、年末でも人が多く、広い駐車場がいっぱいでした。
また犬吠駅まで戻り、通り過ぎてキャベツ畑の中を歩いて地球の丸く見える丘展望館があります。
知らなかったことですが、銚子はキャベツの大産地で、至る所でキャベツを育っています。
他の畑が見当たらないくらいです。

さらに銚子電気鉄道の終点である外川(とかわ)まで歩きました。
銚子の中心部は空襲を受けたこともあるのか広い道で風情はありません。
しかし、この外川地区は斜面に短冊状御区画が拡がり、民家や商店街が並び、静かな街を歩くのが楽しいです。

どうやら紀州の人達が移住してこの碁盤の目の町を作り、ここで挙げられた水産物を運ぶために銚子電気鉄道が作られたようですね。
太平洋岸には屏風ヶ浦と呼ばれる断崖絶壁が拡がっています。
海食崖で、下の部分と上の部分で不連続に時代が違う境界があります。
銚子は隆起していて、とても古い地層が残っているのだそうです。
崖の下には遊歩道が途中まであり、歩くことができます。
銚子は突端にあるので、日の出だけではなく海に沈む夕陽も見ることができます。
太平洋側なのに。

銚子ポートタワーにのぼり、市街を見渡すと、利根川が銚子を避けるように大きく蛇行して太平洋に注いでいる様子、対岸の茨城県の海岸沿いに工業地帯が拡がっている様子がよく見えます。
外房はかつて航海の難所であったため、太平洋岸を北から来た船はここから利根川に入り、江戸に入っていました。
そこで栄えたのが銚子港ということです。
さらに、銚子沖で黒潮と親潮が出会っていることで好漁場でもあります。
ただし、街に港町らしい歴史が残っていないのはちょっと残念。
年末の旅行なので、市場も閉まっていて新鮮な魚介を、とは行きませんが、食べたものは皆美味しく、諺解まで飲食した感じです。
ただ、まあ半島のようなところなので交通はちょっと不便で、電車の本数もそれほど多くないし、車で行くにも高速道路を降りてから結構走る必要があります。
銚子連絡道路というのが建設中で、途中までできているので、それが完成すると良いですね。
富山旅行 [旅・出張]
富山に行ってきました。
昔仕事でしばしば行ったことはあったものの、旅行したことはなかったところなんですよね。
当時は新幹線はなくて、東京からの便は確か6便、B767クラスだったのに、今は3便、それも小型ですね。
東京は晴れていたようですが、到着した富山は雨。
まずは駅から歩いて富岩運河環水公園へ。雨です。

有名な景色の良いスターバックスがあり、混んでいました。雨で景色良くないですが。
ちなみに富岩は富岩と呼び、富山と岩瀬を結んでいるという意味。
富山港線で富山駅から東岩瀬に行ってみました。
東岩瀬は、富山市街を流れる神通川の河口で、富山港があるところです。
かつては北前船が通り、栄えたところ。
重要伝統的建造物保存地区に指定されていませんが、良いところですね。
旧森家住宅と旧馬場家住宅が並んであり、中を見学することができます。

特に旧馬場家住宅は解説も詳しいです。
馬場はるという人物がいて、北前船で成した財産を寄付して高等学校ができ、それが富山大学の人文系になっているとのこと。
お金持ちになって人材育成に金を使うのは一番格好いいですね。下品にお金を配ったり散財するのではなく。
さらに雨がひどい。
ちなみに「東」岩瀬という地名。
なんと江戸時代に神通川の河口が洪水で変わって東に移動し、そこでこの港と街ができたようです。
高さ20mの展望台に上って街を見渡すことが出来ます。
エレベーターがなく登るのは大変ですが、良い景色です。

東岩瀬からの戻りは富岩水上ライン。

これもなかなか楽しいです。
富山港から神通川に沿って水路があって、そこを通って富岩運河環水公園まで行きます。
途中にパナマ運河と同じ閘門があり、水位を上げて調整していきます。これも楽しい経験でした。
なお、この船はこの季節で終わり。そして、夏も水草が生えすぎると水路を通れなくなったりするそうです。
富山市街も歩いてみました。
街の真ん中には富山城址があります。
鉄筋コンクリートの天守閣が建っていて、城の歴史の博物館になっています。

神通川はかつて大きく蛇行して富山市街を通っており、この城も川沿い、自然堤防の上に建っていたらしい。
その後、川はショートカットさせて市街を通らないようにし、埋め立てた旧河道に市役所などを建てたとのこと。
これは富山市役所の展望台に上ってみるとよくわかります。
市役所自体埋め立てた旧河道に経っていて、写真の正面から大きく左方向に旧河道が曲がり、高いビルは旧河道の上に並んで弧を描いています。
富岩運河環水公園もこの旧河道の残り部分だそうです。

しかし、この市役所の展望台、作った人偉いと思います。
普通市役所に展望台を作るなんて言ったら、無駄遣いするな、という話になりそうです。
また、展望台からは360度を見渡すことが出来ますが、エレベーターを降りた向きが館山方向というのも気が利いています。
富山の街は紅葉が進んでいました。
東京に比べると随分気温も低いです。

市内は寂れている感は全くなく、駅の周りもホテルが建ち並び、人も多く、街も新しくてきれいです。
コンパクトシティで有名で、路面電車で快適に移動できます。

駅周辺の他、総曲輪(そうがわ)にも商店街があり、空き店舗があるものの、SOGAWA BASEというおしゃれなビルもありました。
夜の歓楽街も賑やかでした。
もちろん、鮨も美味しかった。香箱ガニも、普通のイワシも。
このためだけにまた来ても良いと思いました。
帰りも飛行機。
天気に恵まれなかったけれど、帰る日は晴れて、すばらしい景色でした。
たしか、市の南側に自衛隊の訓練空域があるので底を越えるために大回りするのですよね。
国内線には色々乗っていますが、この路線が一番景色が良い気がします。

昔仕事でしばしば行ったことはあったものの、旅行したことはなかったところなんですよね。
当時は新幹線はなくて、東京からの便は確か6便、B767クラスだったのに、今は3便、それも小型ですね。
東京は晴れていたようですが、到着した富山は雨。
まずは駅から歩いて富岩運河環水公園へ。雨です。

有名な景色の良いスターバックスがあり、混んでいました。雨で景色良くないですが。
ちなみに富岩は富岩と呼び、富山と岩瀬を結んでいるという意味。
富山港線で富山駅から東岩瀬に行ってみました。
東岩瀬は、富山市街を流れる神通川の河口で、富山港があるところです。
かつては北前船が通り、栄えたところ。
重要伝統的建造物保存地区に指定されていませんが、良いところですね。
旧森家住宅と旧馬場家住宅が並んであり、中を見学することができます。

特に旧馬場家住宅は解説も詳しいです。
馬場はるという人物がいて、北前船で成した財産を寄付して高等学校ができ、それが富山大学の人文系になっているとのこと。
お金持ちになって人材育成に金を使うのは一番格好いいですね。下品にお金を配ったり散財するのではなく。
さらに雨がひどい。
ちなみに「東」岩瀬という地名。
なんと江戸時代に神通川の河口が洪水で変わって東に移動し、そこでこの港と街ができたようです。
高さ20mの展望台に上って街を見渡すことが出来ます。
エレベーターがなく登るのは大変ですが、良い景色です。

東岩瀬からの戻りは富岩水上ライン。

これもなかなか楽しいです。
富山港から神通川に沿って水路があって、そこを通って富岩運河環水公園まで行きます。
途中にパナマ運河と同じ閘門があり、水位を上げて調整していきます。これも楽しい経験でした。
なお、この船はこの季節で終わり。そして、夏も水草が生えすぎると水路を通れなくなったりするそうです。
富山市街も歩いてみました。
街の真ん中には富山城址があります。
鉄筋コンクリートの天守閣が建っていて、城の歴史の博物館になっています。

神通川はかつて大きく蛇行して富山市街を通っており、この城も川沿い、自然堤防の上に建っていたらしい。
その後、川はショートカットさせて市街を通らないようにし、埋め立てた旧河道に市役所などを建てたとのこと。
これは富山市役所の展望台に上ってみるとよくわかります。
市役所自体埋め立てた旧河道に経っていて、写真の正面から大きく左方向に旧河道が曲がり、高いビルは旧河道の上に並んで弧を描いています。
富岩運河環水公園もこの旧河道の残り部分だそうです。

しかし、この市役所の展望台、作った人偉いと思います。
普通市役所に展望台を作るなんて言ったら、無駄遣いするな、という話になりそうです。
また、展望台からは360度を見渡すことが出来ますが、エレベーターを降りた向きが館山方向というのも気が利いています。
富山の街は紅葉が進んでいました。
東京に比べると随分気温も低いです。

市内は寂れている感は全くなく、駅の周りもホテルが建ち並び、人も多く、街も新しくてきれいです。
コンパクトシティで有名で、路面電車で快適に移動できます。

駅周辺の他、総曲輪(そうがわ)にも商店街があり、空き店舗があるものの、SOGAWA BASEというおしゃれなビルもありました。
夜の歓楽街も賑やかでした。
もちろん、鮨も美味しかった。香箱ガニも、普通のイワシも。
このためだけにまた来ても良いと思いました。
帰りも飛行機。
天気に恵まれなかったけれど、帰る日は晴れて、すばらしい景色でした。
たしか、市の南側に自衛隊の訓練空域があるので底を越えるために大回りするのですよね。
国内線には色々乗っていますが、この路線が一番景色が良い気がします。

常磐会津旅行 [旅・出張]
福島県の南相馬と会津若松に行ってきました。
この時期旅行に行くとすれば南より北ですよね。紅葉シーズンなので。
今回は車だったのですが、(いつものように)朝寝坊したために結構首都高も混んでいて、東京から出るのに手間取りました。
常磐道を北上し、南相馬に着いたのは夕方。
海に行くと、堤防の内側の湿地のような場所に、夕暮れの中、怖くなるほど多くのトンボが飛んでいました。
泊まったのは原ノ町。
ホテルもレンタカーも数件あり、飲食店もぱらぱらとあって、想像していたより街でした。
当然ながら、刺身も美味しい。
翌朝は南相馬市博物館。
市の博物館としては充実していて、ハイライトは当然のように相馬野馬追としても、先史時代の人類の歴史からこの地の生態系、縄文、弥生、中世、近代と歴史と文化がまとめられていました。
馬だけではなく、かつて浜通りでは砂鉄を使った製鉄も盛んに行われていたようです。

桜井古墳という前方後方墳(前方後円墳ではない)もあって、有力者もいたのでしょう。

大悲山の石仏という観光の名所があり、薬師堂石仏は三尊と2立像の5体があります。
顔こそ摩耗してわからないものの、彩色も一部残っています。

ここには面白い話があって、昔、玉都(たまいち)という盲目の僧がここで毎晩祈ったところ、満願を前にした晩、琵琶を弾いているところに若侍が現れました。
若侍が言うには、自分が大蛇であり、明日からこの地を雨で大沼にして去るつもりだ、お前には言うが、決して他言するな、他言するとお前を殺すと伝えます。
すると、次は観音様が現れ、殿様にそれを伝えて民を救えと諭します。
迷った玉都は殿様に伝えて命を失い、大蛇は無事に退治された、という話です。
単純な昔話ではなく、過去の何らかの災害を伝えているような気もします。
その後、西に大きく移動、紅葉の中をドライブし、裏磐梯を経由して、会津若松へ。
裏磐梯にはスモールマウスバスの釣り場として有名な桧原湖や五色沼などいくつもの湖沼がありますが、なんとこれらは1888年に噴火と共に山体崩壊が起き、できたものとのこと。当然人も多く亡くなりました。
こんなに新しい湖だとは知りませんでした。
そして会津若松は、お約束の白虎隊自刃の地を訪問。
観光客多し。

そして、福島県立博物館を見て鶴ヶ丘城。
天守閣は昭和40年代にできたもののようで、当然コンクリート造り。
ただ、それ以外の石垣はとても立派なものが残っていますし、そもそも城址が他の用途に利用されていなかったようですね。

最後は大内宿(おおうちじゅく)
重要伝統的建造物保存地区として楽しみにしていたところでここも紅葉シーズンで車も渋滞。
建物自体は茅葺きで趣があるものの、どの建物も観光客向けの土産物屋や蕎麦屋でした。
他の重伝建では人が住んでいて中も見られないことも多く、どっちもどっちですね。

3日で走行距離は800km近く、新幹線だとあっという間に通り過ぎてしまう福島県、広いですね。
この時期旅行に行くとすれば南より北ですよね。紅葉シーズンなので。
今回は車だったのですが、(いつものように)朝寝坊したために結構首都高も混んでいて、東京から出るのに手間取りました。
常磐道を北上し、南相馬に着いたのは夕方。
海に行くと、堤防の内側の湿地のような場所に、夕暮れの中、怖くなるほど多くのトンボが飛んでいました。
泊まったのは原ノ町。
ホテルもレンタカーも数件あり、飲食店もぱらぱらとあって、想像していたより街でした。
当然ながら、刺身も美味しい。
翌朝は南相馬市博物館。
市の博物館としては充実していて、ハイライトは当然のように相馬野馬追としても、先史時代の人類の歴史からこの地の生態系、縄文、弥生、中世、近代と歴史と文化がまとめられていました。
馬だけではなく、かつて浜通りでは砂鉄を使った製鉄も盛んに行われていたようです。

桜井古墳という前方後方墳(前方後円墳ではない)もあって、有力者もいたのでしょう。

大悲山の石仏という観光の名所があり、薬師堂石仏は三尊と2立像の5体があります。
顔こそ摩耗してわからないものの、彩色も一部残っています。

ここには面白い話があって、昔、玉都(たまいち)という盲目の僧がここで毎晩祈ったところ、満願を前にした晩、琵琶を弾いているところに若侍が現れました。
若侍が言うには、自分が大蛇であり、明日からこの地を雨で大沼にして去るつもりだ、お前には言うが、決して他言するな、他言するとお前を殺すと伝えます。
すると、次は観音様が現れ、殿様にそれを伝えて民を救えと諭します。
迷った玉都は殿様に伝えて命を失い、大蛇は無事に退治された、という話です。
単純な昔話ではなく、過去の何らかの災害を伝えているような気もします。
その後、西に大きく移動、紅葉の中をドライブし、裏磐梯を経由して、会津若松へ。
裏磐梯にはスモールマウスバスの釣り場として有名な桧原湖や五色沼などいくつもの湖沼がありますが、なんとこれらは1888年に噴火と共に山体崩壊が起き、できたものとのこと。当然人も多く亡くなりました。
こんなに新しい湖だとは知りませんでした。
そして会津若松は、お約束の白虎隊自刃の地を訪問。
観光客多し。

そして、福島県立博物館を見て鶴ヶ丘城。
天守閣は昭和40年代にできたもののようで、当然コンクリート造り。
ただ、それ以外の石垣はとても立派なものが残っていますし、そもそも城址が他の用途に利用されていなかったようですね。

最後は大内宿(おおうちじゅく)
重要伝統的建造物保存地区として楽しみにしていたところでここも紅葉シーズンで車も渋滞。
建物自体は茅葺きで趣があるものの、どの建物も観光客向けの土産物屋や蕎麦屋でした。
他の重伝建では人が住んでいて中も見られないことも多く、どっちもどっちですね。

3日で走行距離は800km近く、新幹線だとあっという間に通り過ぎてしまう福島県、広いですね。
与那国島旅行 [旅・出張]
ここのところストレスが溜まることが多く、何でも良いから遠くに行きたい(逃げたい)、でもまだ海外は怖い、ということで、与那国島に行ってきました。
日本の大きい島17(上位20位のうち、択捉島、国後島、色丹島の3等をのぞいたもの)を達成したので、思いついた島に自由に旅行です。
与那国島って、人口1700人に満たない、面積も30km2に満たない、小さな島です。
車ならば1時間もあれば一周でき、集落も3つほど。
でも、なぜか知名度高いですよね。何ででしょうか。
往きは那覇経由。
羽田から那覇までの便で、初めてA350XWBに乗りました。
離陸も衝撃音がなくふわっという感じ。
那覇で乗り換えて与那国空港、レンタカーを借りました。
この時点で猛烈な暑さ。
とりあえず西に向かうと久部良という集落があり、久部良バリという標識。
何だと思って行ってみると誰もおらず、割れ目がありました。
かつて人頭税が課されていた頃、妊婦にここを飛び越えさせて命を落とさせたり、流産させたりして口減らしをしていたという。
妊婦じゃなくても、飛び越えるのはちょっと怖いし、滑りそう。

そして最西端。西崎灯台。
ちなみに西崎と書いて「いりざき」。
西の特別な読み方かと思ったらそういう難しい話ではなく、太陽が入るのでいりざきという名前だそうです。
こうしたところに来るといつも天気が悪いのに、一瞬日没が見えました。
この後は下の雲に対応が隠れてしまった。

ちなみに与那国島は何につけても「最西端の・・・」が有名。
しかし、この手のものは厳密にやると、日本が実効支配している・・・とか、一般人が立ち入れる範囲で・・・とか色々注釈がつきます。
まず1泊、期待に反して夜も暑く、冷房を入れないと眠れなかった。
翌朝はティンダバナ(ティンダハナタ)へ。
泊まった祖納(そない)集落の背後にそそり立っている壁のような崖です。
車で行けるところまで行ってちょっと登山道のようなところを歩くのですが、入口にはなぜか③つの説明書きがあり、そして全部名前が違う。謎です。

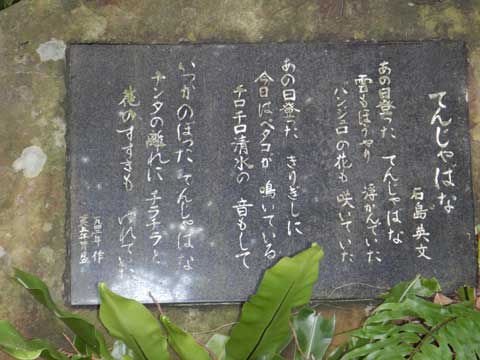

そもそも与那国の言葉はかなで書いてあってもさっぱり意味がわかりません。
方言を話す人には出会わなかったけれど。
このティンダバナ(ティンダハナタ)からは祖納集落と海が一望できます。
そして今度は東崎(あがりざき)。
日が上がる崎だからあがりざき。
突き出た地形には与那国馬がいて、一心不乱に草を食んでいる。
草ってそんなに美味しいの?

さて、私は漫画もドラマも見ていないのですが、Dr.コトー診療所というドラマのためにわざわざ作った診療所が残されています。
中も含めてよく出来ていて、年季の入り方や、貼り付けられているポスターなど、本物の診療所のように見えます。
しばらく見ていると、ようやく人工的な古さなのかな、と思えてくる。
本当の診療所ではなくわざわざ作ったってすごいですよね。
一応観光スポットになっていますが、無人。
入場料は瓶に入れる。
あ、お釣りがないや、と思ったら、お釣りの小銭が入った容器が置いてあるので、そこからとる。
小さな島だから1日あれば全部見終わってしまいますよね。
最終日は意味なくドライブしました。
外に出ると暑さと日差しで耐えられないし、かといって涼めるような施設はないです。
まあ、特に島の南東部は起伏ある道から海が見えてドライブが楽しいですが。
そして、車で走っていて一番驚いたのは墓や墓地でした。
浦野墓地に固まっているほか、道沿いにも巨大なものが突然あったり。
巨大で何も名前とか彫られていなかったりするので、最初何かの施設かと思いました。
この墓地で肝試しとかしたら怖いだろうな・・・。


最後は海を見て、帰りました。

写真を見ると、きれいだけど、とにかく暑かった。
気温は東京と同じくらいなのに、羽田に帰ってきたら涼しかった。
湿度とかもあるのでしょうか。
冬に行くと良いかも。
日本の大きい島17(上位20位のうち、択捉島、国後島、色丹島の3等をのぞいたもの)を達成したので、思いついた島に自由に旅行です。
与那国島って、人口1700人に満たない、面積も30km2に満たない、小さな島です。
車ならば1時間もあれば一周でき、集落も3つほど。
でも、なぜか知名度高いですよね。何ででしょうか。
往きは那覇経由。
羽田から那覇までの便で、初めてA350XWBに乗りました。
離陸も衝撃音がなくふわっという感じ。
那覇で乗り換えて与那国空港、レンタカーを借りました。
この時点で猛烈な暑さ。
とりあえず西に向かうと久部良という集落があり、久部良バリという標識。
何だと思って行ってみると誰もおらず、割れ目がありました。
かつて人頭税が課されていた頃、妊婦にここを飛び越えさせて命を落とさせたり、流産させたりして口減らしをしていたという。
妊婦じゃなくても、飛び越えるのはちょっと怖いし、滑りそう。

そして最西端。西崎灯台。
ちなみに西崎と書いて「いりざき」。
西の特別な読み方かと思ったらそういう難しい話ではなく、太陽が入るのでいりざきという名前だそうです。
こうしたところに来るといつも天気が悪いのに、一瞬日没が見えました。
この後は下の雲に対応が隠れてしまった。

ちなみに与那国島は何につけても「最西端の・・・」が有名。
しかし、この手のものは厳密にやると、日本が実効支配している・・・とか、一般人が立ち入れる範囲で・・・とか色々注釈がつきます。
まず1泊、期待に反して夜も暑く、冷房を入れないと眠れなかった。
翌朝はティンダバナ(ティンダハナタ)へ。
泊まった祖納(そない)集落の背後にそそり立っている壁のような崖です。
車で行けるところまで行ってちょっと登山道のようなところを歩くのですが、入口にはなぜか③つの説明書きがあり、そして全部名前が違う。謎です。

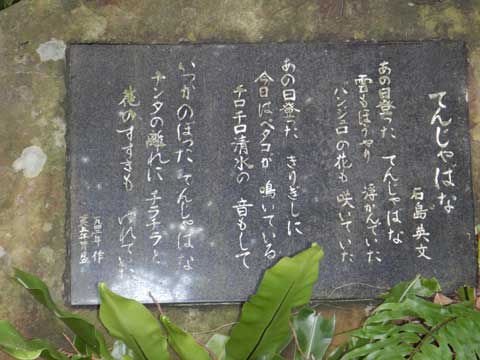

そもそも与那国の言葉はかなで書いてあってもさっぱり意味がわかりません。
方言を話す人には出会わなかったけれど。
このティンダバナ(ティンダハナタ)からは祖納集落と海が一望できます。
そして今度は東崎(あがりざき)。
日が上がる崎だからあがりざき。
突き出た地形には与那国馬がいて、一心不乱に草を食んでいる。
草ってそんなに美味しいの?

さて、私は漫画もドラマも見ていないのですが、Dr.コトー診療所というドラマのためにわざわざ作った診療所が残されています。
中も含めてよく出来ていて、年季の入り方や、貼り付けられているポスターなど、本物の診療所のように見えます。
しばらく見ていると、ようやく人工的な古さなのかな、と思えてくる。
本当の診療所ではなくわざわざ作ったってすごいですよね。
一応観光スポットになっていますが、無人。
入場料は瓶に入れる。
あ、お釣りがないや、と思ったら、お釣りの小銭が入った容器が置いてあるので、そこからとる。
小さな島だから1日あれば全部見終わってしまいますよね。
最終日は意味なくドライブしました。
外に出ると暑さと日差しで耐えられないし、かといって涼めるような施設はないです。
まあ、特に島の南東部は起伏ある道から海が見えてドライブが楽しいですが。
そして、車で走っていて一番驚いたのは墓や墓地でした。
浦野墓地に固まっているほか、道沿いにも巨大なものが突然あったり。
巨大で何も名前とか彫られていなかったりするので、最初何かの施設かと思いました。
この墓地で肝試しとかしたら怖いだろうな・・・。


最後は海を見て、帰りました。

写真を見ると、きれいだけど、とにかく暑かった。
気温は東京と同じくらいなのに、羽田に帰ってきたら涼しかった。
湿度とかもあるのでしょうか。
冬に行くと良いかも。
舞鶴旅行 [旅・出張]
少々時間が経ってしまいましたが、7月に舞鶴に行ってきました。
関西に車で行く別の用事(釣りとも言う)があり、ついでに行ってきました。
舞鶴のあたり、東京からだと行きにくく、鉄道でも結構時間がかかります。
今回はさらに車だったのでなかなかのロングドライブでした。
舞鶴、どこに泊まろうかと調べると、東舞鶴と西舞鶴というのが出てきます。
どちらもそこそこの町で、2つの町が双子のようにある珍しい町です。
と言っても、両者は性格が大きく異なっています。
まずは東舞鶴。
舞鶴引揚記念館を見て、舞鶴赤れんがパークを見て、ガイドツアーに参加し、湾内クルーズも乗りました。
あまりにクソ暑く、アウトドアでもないので日焼け止めをさぼっていたら、外を歩いただけでひどい日焼けとなってしまいました。
東舞鶴はわずか150年の歴史の新しい町で、海軍の町として発展してきました。
基地があり、港には軍艦が泊まっていて、肉じゃがとカレーが名物です。
碁盤の目になっている町の南北の通りは軍艦の名前になっているという徹底ぶり。
「八島」の商店街ではイベントをやっていました。
赤レンガパークは、海軍の武器庫だったところで、一部が再開発されて店、博物館などが入っています。
多くある赤れんがの倉庫は、明治に作られたもの、大正に作られたものと、微妙に様式が異なり、公開されていないものもあります。
かつてはそれぞれから線路が延びていたそうです。
また、所々黒いところが残っているのは、戦時中にカモフラージュのためにタールを塗ったかららしい。
赤レンガパークの前の道路も妙に広く、軍事的な役割もあったようです。


東舞鶴と西舞鶴の間には五老スカイタワーという展望台があります。
舞鶴が天然の良港であることがよくわかります。
逆Y字のように深い入り江が拡がっており、そのYの両方の頂点に東舞鶴と西舞鶴があります。

さて、次は西舞鶴。
実はこちらが本渓舞鶴?
新しい町である東舞鶴に対して、こちらは田辺城を中心とする、戦国時代に坂の織る城下町です。
田辺城の別名が舞鶴城(ぶがくじょう)で、田辺という地名は他にもあることから、明治時代に舞鶴としたそうです。
その後、周辺に新舞鶴とか中舞鶴とか東舞鶴とか似た名前の町ができていき、結局合併して今の舞鶴市になっています。
田辺城跡公園になっていて行きましたが、あまりにクソ暑いので誰もいませんでした。

吉原入江と呼ばれる地区は古い街並みで、水路に向かって出入り口があって船があり、渋い銭湯があります(入らなかったけど)。

関西に車で行く別の用事(釣りとも言う)があり、ついでに行ってきました。
舞鶴のあたり、東京からだと行きにくく、鉄道でも結構時間がかかります。
今回はさらに車だったのでなかなかのロングドライブでした。
舞鶴、どこに泊まろうかと調べると、東舞鶴と西舞鶴というのが出てきます。
どちらもそこそこの町で、2つの町が双子のようにある珍しい町です。
と言っても、両者は性格が大きく異なっています。
まずは東舞鶴。
舞鶴引揚記念館を見て、舞鶴赤れんがパークを見て、ガイドツアーに参加し、湾内クルーズも乗りました。
あまりにクソ暑く、アウトドアでもないので日焼け止めをさぼっていたら、外を歩いただけでひどい日焼けとなってしまいました。
東舞鶴はわずか150年の歴史の新しい町で、海軍の町として発展してきました。
基地があり、港には軍艦が泊まっていて、肉じゃがとカレーが名物です。
碁盤の目になっている町の南北の通りは軍艦の名前になっているという徹底ぶり。
「八島」の商店街ではイベントをやっていました。
赤レンガパークは、海軍の武器庫だったところで、一部が再開発されて店、博物館などが入っています。
多くある赤れんがの倉庫は、明治に作られたもの、大正に作られたものと、微妙に様式が異なり、公開されていないものもあります。
かつてはそれぞれから線路が延びていたそうです。
また、所々黒いところが残っているのは、戦時中にカモフラージュのためにタールを塗ったかららしい。
赤レンガパークの前の道路も妙に広く、軍事的な役割もあったようです。


東舞鶴と西舞鶴の間には五老スカイタワーという展望台があります。
舞鶴が天然の良港であることがよくわかります。
逆Y字のように深い入り江が拡がっており、そのYの両方の頂点に東舞鶴と西舞鶴があります。

さて、次は西舞鶴。
実はこちらが本渓舞鶴?
新しい町である東舞鶴に対して、こちらは田辺城を中心とする、戦国時代に坂の織る城下町です。
田辺城の別名が舞鶴城(ぶがくじょう)で、田辺という地名は他にもあることから、明治時代に舞鶴としたそうです。
その後、周辺に新舞鶴とか中舞鶴とか東舞鶴とか似た名前の町ができていき、結局合併して今の舞鶴市になっています。
田辺城跡公園になっていて行きましたが、あまりにクソ暑いので誰もいませんでした。

吉原入江と呼ばれる地区は古い街並みで、水路に向かって出入り口があって船があり、渋い銭湯があります(入らなかったけど)。

三宅島旅行 [旅・出張]
月が変わってしまいましたが、GW前の4月、三宅島に行ってきました。
伊豆諸島としては、伊豆大島、八丈島に続いて3番目です。
伊豆諸島はフィリピン海プレートの上にあり、太平洋プレートが沈み込むことによってできた火山島です。
中でも三宅島は多くの人の記憶にあるように活発な火山で、直近では1940年、1962年、1983年、2000年とほぼ20年間隔で(大きな)噴火を起こしています。
2000年の噴火では、全島民約3,800人が4年5か月の間島外避難を強いられました。
活発な火山が作る地形、そこからの植生を含めた生態系の復活が繰り返されています。
そうした一見「住みづらい」島のように見えて、この地域の主要な神社が多く残るなど、伊豆諸島の中でも古くから人が集まっていた島でもあるようです。
今回は週末を利用した旅だったので、金曜日に仕事を終えてから竹芝桟橋に行って出航。
伊豆諸島への船は、近めの大島等を回る航路と、遠目の八丈島まで行く航路の2系統があり、今回は後者。
出発時から雨が降っていたものの、夜に東京を出航するのはなかなか良い雰囲気です。

船室は選べ、往路は夜行なので、特2等という昔の寝台列車のような二段ベッド。
これはなかなかいいかも。
湾内はそうでもないですが、外海に出るとそれなりに揺れます。
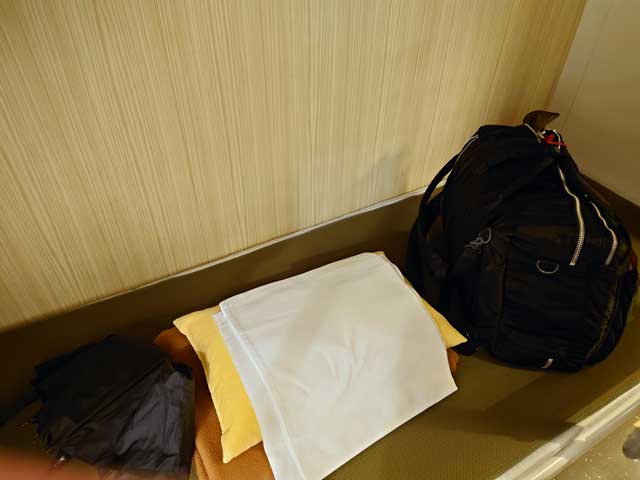
5:00に三宅島の錆ヶ浜港に到着。天気が悪い。

船はこの後御蔵島には着岸せず、八丈島に直行するとのこと。
三宅島は港が3つあり、風や波の状況で直前に着岸する港が決まります。
御蔵島は1つなので欠航しやすいとのこと。
降りる人は釣り竿を持った人ばかり。
早朝なので送迎してもらって宿で二度寝して朝食後、レンタカーを借りてスタート。
まずは西側を中心に。
島の中央部は2000年の噴火以降入れないので、島の周縁部が中心となります。
「天気が良ければ夕陽がきれいなのにねえ。」
いつものことですが・・・。

廃校した小学校が図書館となり、郷土資料館が併設されています。
離島というと島流し。
大島は軽犯罪、三宅島は破廉恥罪、八丈島は政治犯という区分があったそうです。
破廉恥罪とは何なのか。謎は深まります。
阿古地区には火山体験遊歩道があります。
ここには集落があったのですが、1983年の噴火で一夜にして溶岩に飲み込まれました。
このスピードなのでギリギリだったようですが、住民は避難して助かりました。
しかし、温泉が湧き、観光で栄えた集落は消失しました。
集落の海側に小学校と中学校があり、その建物がまるでダムのように溶岩をせき止めています。
遊歩道が設置されて何もない溶岩の上を歩けます。
何もないですが、ハチジョウイタドリを始めとして松が生え始め、植生がゆっくり回復していることがわかります。


また、三宅島には新澪池(しんりょういけ)という池が1763年の噴火の火口湖として形成され、観光地となっていましたが、これまた1983年の噴火で水蒸気爆発して「一瞬にして消え去った」とのこと。
激しすぎる。
翌日は前日よりもさらに天気が悪化。
時折夕立のような強い雨が降る中、東側を中心に。
このあたりは1940年の噴火で22時間で海中からひょうたん山と呼ばれる山ができ、さらに1962年(昭和37年)の噴火で埋め尽くされ三七山という山ができた。

椎取神社(しいとりじんじゃ)は2000年の噴火で社と鳥居が埋没。
このあたりには天然の良港(入江)があったらしいが埋没。

三宅島、周回道路はとても良く整備されていて、これでもかというくらいに公衆トイレもあります。
そして、火山関連の説明もとてもよく整備されています。
サタドー岬はなかなかの絶景でほんやりと御蔵島が見える。

御蔵島はこのようにお椀を伏せたような形で、(行ったことがないけれど)いかにも港が作りにくそうです。
なので1つしかないのか。
記録に残る噴火がない御蔵島に比べて、活発な三宅島は海岸線の変化も激しく、逆に言えば港を作れる海岸部の「傾斜」を作り出すことにもなっているようです。
帰りの船は昼出発。
錆ヶ浜港にはきれいな港湾施設が建っているものの、食事ができるところがないので、港近くの店でのり弁当とメンチカツ2つを買ってきて昼食。
人間も乗り込みますが、コンテナの積み込みもかなりやっていて、これに時間がかかったのか、15分ほど遅れての出航でした。

帰りは一番安い2等和室。船底で窓もありませんでした。

三宅島自体、鳥を見に来ている人を見ましたが、帰りの船もデッキで鳥を探している人がたくさんいました。
アホウドリ?でしょうか。
そしで、帰りの船で、旅に出て初めて、雲間から太陽が覗くのを見ました・・・。
次は「きれいな夕陽」を見に来たいですね。
伊豆諸島としては、伊豆大島、八丈島に続いて3番目です。
伊豆諸島はフィリピン海プレートの上にあり、太平洋プレートが沈み込むことによってできた火山島です。
中でも三宅島は多くの人の記憶にあるように活発な火山で、直近では1940年、1962年、1983年、2000年とほぼ20年間隔で(大きな)噴火を起こしています。
2000年の噴火では、全島民約3,800人が4年5か月の間島外避難を強いられました。
活発な火山が作る地形、そこからの植生を含めた生態系の復活が繰り返されています。
そうした一見「住みづらい」島のように見えて、この地域の主要な神社が多く残るなど、伊豆諸島の中でも古くから人が集まっていた島でもあるようです。
今回は週末を利用した旅だったので、金曜日に仕事を終えてから竹芝桟橋に行って出航。
伊豆諸島への船は、近めの大島等を回る航路と、遠目の八丈島まで行く航路の2系統があり、今回は後者。
出発時から雨が降っていたものの、夜に東京を出航するのはなかなか良い雰囲気です。

船室は選べ、往路は夜行なので、特2等という昔の寝台列車のような二段ベッド。
これはなかなかいいかも。
湾内はそうでもないですが、外海に出るとそれなりに揺れます。
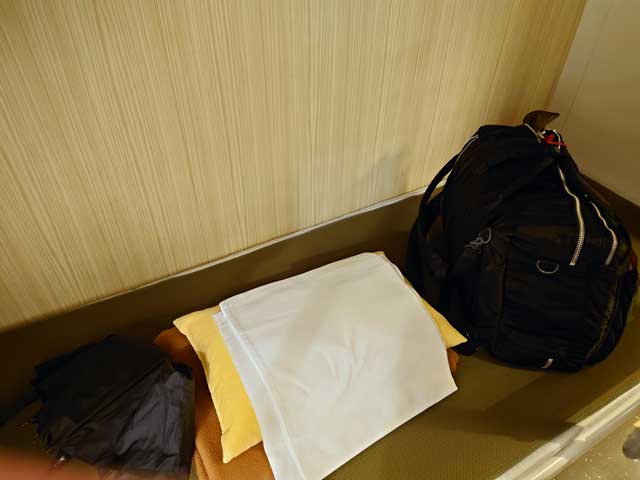
5:00に三宅島の錆ヶ浜港に到着。天気が悪い。

船はこの後御蔵島には着岸せず、八丈島に直行するとのこと。
三宅島は港が3つあり、風や波の状況で直前に着岸する港が決まります。
御蔵島は1つなので欠航しやすいとのこと。
降りる人は釣り竿を持った人ばかり。
早朝なので送迎してもらって宿で二度寝して朝食後、レンタカーを借りてスタート。
まずは西側を中心に。
島の中央部は2000年の噴火以降入れないので、島の周縁部が中心となります。
「天気が良ければ夕陽がきれいなのにねえ。」
いつものことですが・・・。

廃校した小学校が図書館となり、郷土資料館が併設されています。
離島というと島流し。
大島は軽犯罪、三宅島は破廉恥罪、八丈島は政治犯という区分があったそうです。
破廉恥罪とは何なのか。謎は深まります。
阿古地区には火山体験遊歩道があります。
ここには集落があったのですが、1983年の噴火で一夜にして溶岩に飲み込まれました。
このスピードなのでギリギリだったようですが、住民は避難して助かりました。
しかし、温泉が湧き、観光で栄えた集落は消失しました。
集落の海側に小学校と中学校があり、その建物がまるでダムのように溶岩をせき止めています。
遊歩道が設置されて何もない溶岩の上を歩けます。
何もないですが、ハチジョウイタドリを始めとして松が生え始め、植生がゆっくり回復していることがわかります。


また、三宅島には新澪池(しんりょういけ)という池が1763年の噴火の火口湖として形成され、観光地となっていましたが、これまた1983年の噴火で水蒸気爆発して「一瞬にして消え去った」とのこと。
激しすぎる。
翌日は前日よりもさらに天気が悪化。
時折夕立のような強い雨が降る中、東側を中心に。
このあたりは1940年の噴火で22時間で海中からひょうたん山と呼ばれる山ができ、さらに1962年(昭和37年)の噴火で埋め尽くされ三七山という山ができた。

椎取神社(しいとりじんじゃ)は2000年の噴火で社と鳥居が埋没。
このあたりには天然の良港(入江)があったらしいが埋没。

三宅島、周回道路はとても良く整備されていて、これでもかというくらいに公衆トイレもあります。
そして、火山関連の説明もとてもよく整備されています。
サタドー岬はなかなかの絶景でほんやりと御蔵島が見える。

御蔵島はこのようにお椀を伏せたような形で、(行ったことがないけれど)いかにも港が作りにくそうです。
なので1つしかないのか。
記録に残る噴火がない御蔵島に比べて、活発な三宅島は海岸線の変化も激しく、逆に言えば港を作れる海岸部の「傾斜」を作り出すことにもなっているようです。
帰りの船は昼出発。
錆ヶ浜港にはきれいな港湾施設が建っているものの、食事ができるところがないので、港近くの店でのり弁当とメンチカツ2つを買ってきて昼食。
人間も乗り込みますが、コンテナの積み込みもかなりやっていて、これに時間がかかったのか、15分ほど遅れての出航でした。

帰りは一番安い2等和室。船底で窓もありませんでした。

三宅島自体、鳥を見に来ている人を見ましたが、帰りの船もデッキで鳥を探している人がたくさんいました。
アホウドリ?でしょうか。
そしで、帰りの船で、旅に出て初めて、雲間から太陽が覗くのを見ました・・・。
次は「きれいな夕陽」を見に来たいですね。
大崎上島としまなみ海道旅行 [旅・出張]
瀬戸内の大崎上島としまなみ海道に行ってきました。
毎年年度末が仕事の繁忙期ですが、今年は少し早めに片付いたため、3月末の平日に旅行して見ました。
社会人になってからは初めてかも知れません。
日本の大きな島20(北方領土をのぞいた17)は全部行ってしまったので、自由に島を選びました。
以前大崎下島の御手洗に行ったとき、となりに大崎上島という島があり、木江という町があることを知り、気にはなっていました。
大崎上島町は、今住んでいる武蔵野市の友好都市でもあります。
いつものように島でレンタカーを借りようと調べると、なんとレンタカーがない。
バスで回るのも不便だしな、と思ったところ、フェリーがあることに気がつき、島外で車を借りて上陸することにしました。
そして地図を見ると、帰りは隣の大三島に渡れば、しまなみ海道で戻ってくることができることに気がつきました。
一筆書き信奉者としてはたまらないコースです。
出発時の東京は珍しく雨、そして平日なので空港までの電車はちょっと大変。
でも、広島空港に着陸すると(珍しく)良い天気。
空港でレンタカーを借り、竹原港まで行ってフェリー。

フェリーなんて久し振り。自分で運転して乗るのは初めて。
車検証を持って切符売場に行き、車の長さに応じた料金を支払い、指定された場所で車の列に並び、指示に従って乗り込む。
ちょっとどきどきです。
フェリー自体は出航して20分で大崎上島に到着。
あっけないです。
港近くに海と島の歴史資料館 大望月館(おおおもちづきかん)があり、島について知ることができます。
この建物の当主は廻船問屋として発展し、議員にもなったとのこと。
8月の櫂伝馬競漕(かいでんまきょうそう)が島の行事のハイライトのようですね。
何もない離島と思いきや、木造船の時代から造船業が盛んで、ピーク時には29もの造船所が島内にあったそうです。
また、航海の学校も作ってしまって、今は広島商船高等専門学校になっています。
広島県立広島叡智学園という学校もあって、二十歳前の男性が多いという変わった人口構成になっています。
日が落ちる前に、神峰山(かんのみねやま)に登ってみました。
竹原、本州が見え、今治、四国が見え、しまなみ海道の端が見えます。
特に四国側は多くの船が往来しているのが見えます。
そして、静か・・・ではなく、遠くから造船所の音が聞こえます。


周りにも島があって、これまで旅行してきた「離島」とは雰囲気が違います。
東側に隣接する島々はしまなみ海道で尾道、今治と連結され、
西側に隣接する島々はとびしま海道で呉と連結されています。
結果、真ん中の大崎上島だけ、本州四国と架橋されていないという状況。
せっかくだから、隣の島まで橋を架けて、しまなみ海道やとびしま海道と連結してしまえば良いのに、と思いますが、例え橋を架けても尾道、今治、呉にはそれなりの時間がかかり、一方、フェリーは頻発していて竹原へと20分で本州に到達できるので、微妙ですね。
島の東側には木江という町があり、隣の大崎下島の御手洗同様栄えたところです。
木造船の技術があったからでしょうか、木造の3階建や5階建の家が残っています。

ただし、重要伝統的建造物保存地区となった御手洗と比較して、現存している建物はわずかであり、空き家となっているのか崩壊している3階建の建物もありました。
最後の日はまたフェリーで今度は大三島へ。

人口こそ大崎上島より少ないものの、しまなみ海道による交流人口が多いせいか、コンビニもあるし、喫茶店やレストランもあるし、急に都会です。
大山祇神社という立派な神社があります。
島にあるのに、伊予国一宮だそうです。
そう、大三島は愛媛県(今治市)なのですね。

隣の生口島は瀬戸田が中心で、耕三寺(こうさんじ)や向上寺(こうじょうじ)があります。


以前しまなみ海道を通ったときはバスだったので、こちらまで足を伸ばせませんでした。
こちらも観光客が多く、食堂や民宿も集まり、都会です。架橋の効果は大きい。
瀬戸田は柑橘類推しで、さらに平山郁夫美術館もありました。
平山郁夫、小学校の時から絵がかなり上手です。
瀬戸田で時間を食ってしまったので、因島と向島は泣く泣く通過して空港へ。
また来なければなりませんね。
毎年年度末が仕事の繁忙期ですが、今年は少し早めに片付いたため、3月末の平日に旅行して見ました。
社会人になってからは初めてかも知れません。
日本の大きな島20(北方領土をのぞいた17)は全部行ってしまったので、自由に島を選びました。
以前大崎下島の御手洗に行ったとき、となりに大崎上島という島があり、木江という町があることを知り、気にはなっていました。
大崎上島町は、今住んでいる武蔵野市の友好都市でもあります。
いつものように島でレンタカーを借りようと調べると、なんとレンタカーがない。
バスで回るのも不便だしな、と思ったところ、フェリーがあることに気がつき、島外で車を借りて上陸することにしました。
そして地図を見ると、帰りは隣の大三島に渡れば、しまなみ海道で戻ってくることができることに気がつきました。
一筆書き信奉者としてはたまらないコースです。
出発時の東京は珍しく雨、そして平日なので空港までの電車はちょっと大変。
でも、広島空港に着陸すると(珍しく)良い天気。
空港でレンタカーを借り、竹原港まで行ってフェリー。

フェリーなんて久し振り。自分で運転して乗るのは初めて。
車検証を持って切符売場に行き、車の長さに応じた料金を支払い、指定された場所で車の列に並び、指示に従って乗り込む。
ちょっとどきどきです。
フェリー自体は出航して20分で大崎上島に到着。
あっけないです。
港近くに海と島の歴史資料館 大望月館(おおおもちづきかん)があり、島について知ることができます。
この建物の当主は廻船問屋として発展し、議員にもなったとのこと。
8月の櫂伝馬競漕(かいでんまきょうそう)が島の行事のハイライトのようですね。
何もない離島と思いきや、木造船の時代から造船業が盛んで、ピーク時には29もの造船所が島内にあったそうです。
また、航海の学校も作ってしまって、今は広島商船高等専門学校になっています。
広島県立広島叡智学園という学校もあって、二十歳前の男性が多いという変わった人口構成になっています。
日が落ちる前に、神峰山(かんのみねやま)に登ってみました。
竹原、本州が見え、今治、四国が見え、しまなみ海道の端が見えます。
特に四国側は多くの船が往来しているのが見えます。
そして、静か・・・ではなく、遠くから造船所の音が聞こえます。


周りにも島があって、これまで旅行してきた「離島」とは雰囲気が違います。
東側に隣接する島々はしまなみ海道で尾道、今治と連結され、
西側に隣接する島々はとびしま海道で呉と連結されています。
結果、真ん中の大崎上島だけ、本州四国と架橋されていないという状況。
せっかくだから、隣の島まで橋を架けて、しまなみ海道やとびしま海道と連結してしまえば良いのに、と思いますが、例え橋を架けても尾道、今治、呉にはそれなりの時間がかかり、一方、フェリーは頻発していて竹原へと20分で本州に到達できるので、微妙ですね。
島の東側には木江という町があり、隣の大崎下島の御手洗同様栄えたところです。
木造船の技術があったからでしょうか、木造の3階建や5階建の家が残っています。

ただし、重要伝統的建造物保存地区となった御手洗と比較して、現存している建物はわずかであり、空き家となっているのか崩壊している3階建の建物もありました。
最後の日はまたフェリーで今度は大三島へ。

人口こそ大崎上島より少ないものの、しまなみ海道による交流人口が多いせいか、コンビニもあるし、喫茶店やレストランもあるし、急に都会です。
大山祇神社という立派な神社があります。
島にあるのに、伊予国一宮だそうです。
そう、大三島は愛媛県(今治市)なのですね。

隣の生口島は瀬戸田が中心で、耕三寺(こうさんじ)や向上寺(こうじょうじ)があります。


以前しまなみ海道を通ったときはバスだったので、こちらまで足を伸ばせませんでした。
こちらも観光客が多く、食堂や民宿も集まり、都会です。架橋の効果は大きい。
瀬戸田は柑橘類推しで、さらに平山郁夫美術館もありました。
平山郁夫、小学校の時から絵がかなり上手です。
瀬戸田で時間を食ってしまったので、因島と向島は泣く泣く通過して空港へ。
また来なければなりませんね。
高知旅行 [旅・出張]
毎年と言いつつ、コロナ禍で中断していた1月連休の旅行、3年ぶりに行ってきました。
目的地は高知。高知市を中心に東西に広がり、一筆書き信奉者としては攻めにくいところです。
実のところ高知市は仕事で何回か行ったことがあり、現存12天守の1つである高知城も行ったことがあります。
そのため、前半は西側、後半は東側に行きました。
まずは高知空港に午前に着いてからレンタカーを借りて西へ向かい、足摺岬へ。
高速道路は未完成のようで、足摺岬まで到達したときには夕方でした。

そこから四万十市中村に宿泊。
ちなみに、四万十市と四万十町があり、両者が隣接しているというややこしさ。
中村の町は小さいものの、飲食店も結構あって、過ごしやすいところだと思いました。
翌日午前は四万十川。
これ、写真やテレビで見たことはあるので、実はあまり期待していなかったのですが、良いですね。
冬は水の透明度が増していて、6-7mくらいの底が見えるのだそうです。
増水時は相当水が増えるようで川原も広いし、本流だけで21本の沈下橋があります。
この沈下橋というのは増水して沈んでも、流木などが引っかからないように、欄干など何もない橋です。
遠くの沈下橋を、自転車が通っていくのを見るととてものどかな感じがします。
しかし、実際に自動車で渡ってみたら、怖くて左右を見る余裕は全くありませんでした。

街灯もないし、夜は絶対怖いですよね。

昼過ぎに再び東に向かい、高知市まで戻って1泊。
最終日は東に向かいました。
高知市から西側に行くときはトンネルが多かったのに対して、高知市から東に向かうと、海沿いを走り、ドライブをしていてとても気持ちがいいです。

途中まで鉄道も並行して走ります。
津波対策として、避難タワーがしばしば目に入るのでぎょっとしますが・・・。
この避難タワー、関東だと九十九里浜で見るくらいですかね。
室戸岬、岬の先端は地味ですが、非常に面白いところです。
室戸世界ジオパークセンターというのもあって、地質・地形の説明もありました。
高知県、というか、四国の南半分は、フィリピン海プレートが沈み込むことによる付加体でできています。
そのため、南に行くほど新しい地質になっています。
そして、室戸岬はどんどん隆起しています。
なので、地震の度に港が浅くなってしまい、大変なのだそうです。
空海が修行し、悟りを開いたことで有名な御蔵洞(御厨人窟:みくろど)という洞窟があります。
これもかつて、空海が修行した1000年前は6mほど低く、海面近くにあったのだそうです。

さらに、こうした隆起によって海成段丘が形成されており、段丘の上も畑として利用されているそうです。
また、台風が通過する場所で風がすさまじいため、民家は要塞のように高い壁で囲われています。
これ、家の中に日が入るんでしょうか、というくらいです。
帰り道には吉良川町(きらがわ)の街並みを見てきました。
林業、製炭で栄えた町で、重要伝統的建造物保存地区に指定されています。
古い建物には水切り瓦といって、壁に何段かの瓦の庇がついています。
これは、大量の降雨を直接地面に落とすことによって漆喰の壁を守るものだそうです。
また、地形も面白く、ここも海成段丘なのか町が2段になっており、海沿いの低いところの家は2階建、その上の段の家は1階建となっています。

室戸は捕鯨も盛んだったそうで、キラメッセ室戸鯨館という小さいけれどきれいな博物館もありました。
3日間、レンタカーの走行距離は500kmを越え、普段はアイサイトのクルーズコントロールに慣れきってしまっているので運転は疲れましたが、移動しただけ距離感や土地の様子がわかって楽しめました。
四万十はまた行っても良いですかね。のんびりと。
目的地は高知。高知市を中心に東西に広がり、一筆書き信奉者としては攻めにくいところです。
実のところ高知市は仕事で何回か行ったことがあり、現存12天守の1つである高知城も行ったことがあります。
そのため、前半は西側、後半は東側に行きました。
まずは高知空港に午前に着いてからレンタカーを借りて西へ向かい、足摺岬へ。
高速道路は未完成のようで、足摺岬まで到達したときには夕方でした。

そこから四万十市中村に宿泊。
ちなみに、四万十市と四万十町があり、両者が隣接しているというややこしさ。
中村の町は小さいものの、飲食店も結構あって、過ごしやすいところだと思いました。
翌日午前は四万十川。
これ、写真やテレビで見たことはあるので、実はあまり期待していなかったのですが、良いですね。
冬は水の透明度が増していて、6-7mくらいの底が見えるのだそうです。
増水時は相当水が増えるようで川原も広いし、本流だけで21本の沈下橋があります。
この沈下橋というのは増水して沈んでも、流木などが引っかからないように、欄干など何もない橋です。
遠くの沈下橋を、自転車が通っていくのを見るととてものどかな感じがします。
しかし、実際に自動車で渡ってみたら、怖くて左右を見る余裕は全くありませんでした。

街灯もないし、夜は絶対怖いですよね。

昼過ぎに再び東に向かい、高知市まで戻って1泊。
最終日は東に向かいました。
高知市から西側に行くときはトンネルが多かったのに対して、高知市から東に向かうと、海沿いを走り、ドライブをしていてとても気持ちがいいです。

途中まで鉄道も並行して走ります。
津波対策として、避難タワーがしばしば目に入るのでぎょっとしますが・・・。
この避難タワー、関東だと九十九里浜で見るくらいですかね。
室戸岬、岬の先端は地味ですが、非常に面白いところです。
室戸世界ジオパークセンターというのもあって、地質・地形の説明もありました。
高知県、というか、四国の南半分は、フィリピン海プレートが沈み込むことによる付加体でできています。
そのため、南に行くほど新しい地質になっています。
そして、室戸岬はどんどん隆起しています。
なので、地震の度に港が浅くなってしまい、大変なのだそうです。
空海が修行し、悟りを開いたことで有名な御蔵洞(御厨人窟:みくろど)という洞窟があります。
これもかつて、空海が修行した1000年前は6mほど低く、海面近くにあったのだそうです。

さらに、こうした隆起によって海成段丘が形成されており、段丘の上も畑として利用されているそうです。
また、台風が通過する場所で風がすさまじいため、民家は要塞のように高い壁で囲われています。
これ、家の中に日が入るんでしょうか、というくらいです。
帰り道には吉良川町(きらがわ)の街並みを見てきました。
林業、製炭で栄えた町で、重要伝統的建造物保存地区に指定されています。
古い建物には水切り瓦といって、壁に何段かの瓦の庇がついています。
これは、大量の降雨を直接地面に落とすことによって漆喰の壁を守るものだそうです。
また、地形も面白く、ここも海成段丘なのか町が2段になっており、海沿いの低いところの家は2階建、その上の段の家は1階建となっています。

室戸は捕鯨も盛んだったそうで、キラメッセ室戸鯨館という小さいけれどきれいな博物館もありました。
3日間、レンタカーの走行距離は500kmを越え、普段はアイサイトのクルーズコントロールに慣れきってしまっているので運転は疲れましたが、移動しただけ距離感や土地の様子がわかって楽しめました。
四万十はまた行っても良いですかね。のんびりと。
前の10件 | -


